サッカーにおけるビルドアップとは?【ゴールを奪うための攻撃設計図】
「ビルドアップ」という言葉をサッカーの解説で耳にする機会が、近年急速に増えたと感じていませんか?「後ろでボールを回しているだけじゃないの?」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は現代サッカーの勝敗を分ける極めて重要な戦術的要素です。このビルドアップを理解することは、試合の流れを読み解き、監督の狙いや選手の意図を深く知るための鍵となります。
本記事では、まず「ビルドアップとは何か?」という根本的な問いに、単なるパス回しとの違いを明確にしながらお答えします。さらに、なぜこれほどまでにビルドアップが重要視されるようになったのか、その背景にあるルール改正や戦術の進化にも触れていきます。ここを読み終える頃には、ビルドアップが単なる守備から攻撃への移行作業ではなく、ゴールを奪うために緻密に設計された「攻撃の設計図」であることが、はっきりとご理解いただけるはずです。
ビルドアップの基本的な定義:単なるパス回しとの決定的な違い
結論から申し上げますと、ビルドアップとは**「ゴールを奪うという最終目的のために、自陣後方から攻撃を組み立て、ボールと選手を計画的に前進させるプロセス」**を指します。英語の”build up”が「構築する、組み立てる」を意味するように、サッカーにおけるビルドアップは、まさに攻撃をゼロから構築していく作業そのものです。
多くの方が混同しがちな「ただのパス回し」との間には、決定的な違いが存在します。その違いとは**「目的意識の有無」**です。
- 目的のないパス回し: 時間稼ぎや、相手のプレッシャーから逃れるためだけに、意図なく横パスやバックパスを繰り返す状態です。ボールは動いていますが、チームとして前進する意図や、相手の守備を崩す狙いは希薄です。
- ビルドアップ: 一つひとつのパスに明確な意図が込められています。例えば、「相手のフォワードをこちらに引きつけて、その背後に生まれたスペースを使おう」「サイドバックを高い位置に押し上げて、ウイングの選手が1対1を仕掛けやすい状況を作ろう」といった具体的な狙いを持ちながら、チーム全体で連動してボールを前進させます 2。
つまり、ビルドアップは守備陣(GKやDF)から始まり、中盤(MF)を経由して、攻撃陣(FW)が有利な状況でボールを受けられるように設計された、一連の組織的なプレーなのです。それは、ゴールという最終目的地へ向かうための、緻密なナビゲーションシステムと言えるでしょう。
なぜ現代サッカーでビルドアップが重要視されるのか?:ルール改正と戦術の進化
現代サッカーにおいてビルドアップが戦術の主流となった背景には、主に2つの大きな要因が絡み合っています。
第一に、2019年のゴールキックに関するルール改正です。この改正により、ゴールキックの際にゴールキーパーが蹴ったボールを、ペナルティエリア内の味方選手が受けられるようになりました 2。以前はエリアの外で受けなければならなかったため、相手選手に高い位置からプレッシャーをかけられ、ボールを失うリスクが高かったのです。しかし、このルール改正によって、ゴールキーパーとセンターバックが自陣の深い位置で安全にパス交換を始められるようになり、後方からのビルドアップが格段に行いやすくなりました。
第二に、「11人全員で攻撃し、11人全員で守る」という戦術思想の進化が挙げられます。かつては守備専門と見なされていたゴールキーパーやセンターバックにも、フィールドプレーヤーと同等のパス精度や戦術眼が求められるようになりました。ゴールキーパーがビルドアップに参加することで、相手のFW(通常1〜2人)に対して、GK+DF(3〜4人)という
数的優位を後方で作りやすくなります 2。この数的優位を活かして相手の第一プレッシャーラインを突破することが、ビルドアップの第一歩となるのです。
これらの要因が組み合わさった結果、単に前線へロングボールを蹴り込む「運任せ」の攻撃ではなく、後方から着実にボールを繋ぎ、チーム全体で相手ゴールに迫るビルドアップが、勝利の確率を高めるための合理的な戦術として世界中のチームに採用されるようになりました。
ビルドアップの3つの主要な目的【ボール保持は出発点にすぎない】
ビルドアップの定義を理解したところで、次はその「目的」について深く掘り下げていきましょう。ビルドアップは、ボールポゼッション率を高めること自体がゴールではありません。それはあくまで出発点であり、その先にはゴールを奪うための3つの明確な目的が存在します。これらの目的を理解することで、一見すると単調に見えるパス回しの中に隠された、チームの高度な戦術的狙いが見えてくるはずです。
目的①:数的優位を作り出し、安全にボールを前進させる
ビルドアップの最も基本的かつ重要な目的は、ピッチの各エリアで数的優位(数的不均衡)を作り出し、安全かつ確実にボールを前進させることです。
サッカーは、相手より1人でも多い状況を作れば、プレーの選択肢が増え、格段に有利になります。ビルドアップでは、特に自陣後方でこの数的優位を意識的に作り出します。前述の通り、ゴールキーパーが攻撃に参加することで、相手の最前線の守備人数を上回ることが可能になります。
例えば、相手が2トップ(FW2人)でプレスをかけてきたとします。こちらがGKと2人のCB(センターバック)で対応すれば、3対2の数的優位が生まれます。この状況では、必ずフリーの選手が1人できるため、プレッシャーを落ち着いて回避し、ボールを中盤へ届けることができます。この小さな数的優位をリレーのように繋いでいくことで、チーム全体が押し上がり、相手陣地深くまで安全にボールを運ぶことが可能になるのです。
目的②:相手を意図的に動かし、守備組織に「ズレ」を生み出す
第二の目的は、より戦術的で、意図的なパス回しによって相手の守備組織を動かし、そこに「ズレ」や「スペース」を生み出すことです。
強固な守備ブロックを組んでいる相手を、真正面から崩すのは至難の業です。そこでビルドアップでは、あえて自陣でゆっくりとボールを保持し、相手を「おびき出す」という駆け引きを行います。相手からすれば、自陣深くまで攻め込まれているのに何もしないわけにはいきません。ボールを奪うために、誰かがポジションを離れてプレスに出てくる必要があります。
この**「相手が動いた瞬間」**こそが、ビルドアップの狙い目です。選手が1人動けば、その選手が元々いた場所には必ずスペースが生まれます。例えば、相手のサイドハーフがこちらのサイドバックに食いついてきたら、そのサイドハーフの背後のスペースががら空きになります。そのスペースに味方の中盤選手が走り込むことで、相手の守備ラインを突破する糸口を見つけるのです。
このように、ビルドアップは相手の守備アクションを逆手に取り、相手を能動的に動かして生まれた歪みを突く、非常に知的な攻撃プロセスと言えます。
目的③:攻撃の再現性を高め、「運」の要素を徹底的に排除する
三つ目の目的は、攻撃の成功確率を高め、再現性のある得点パターンを確立することです。
前線にただロングボールを蹴り込む攻撃は、一見すると手っ取り早く見えます。しかし、そのボールが味方に収まるかどうかは、競り合いの強さやセカンドボールの行方といった「50:50」の不確定要素に大きく左右されます。これでは、安定して得点を奪うことは困難です。
ビルドアップは、この「運」の要素を可能な限り排除するためのアプローチです。後方から丁寧にパスを繋ぐことで、ボールを失う確率を下げ、チームが意図した形で攻撃を展開できます。選手間の距離感をコンパクトに保ちながら前進するため、ボールを失ったとしても、すぐに複数人でプレッシャーをかけて奪い返す「カウンタープレス」に移行しやすいという利点もあります。
チーム全体で「どのような形でボールを前に運び、どこで数的優位を作り、誰がフィニッシュに絡むのか」という共通認識を持つことで、トレーニングで繰り返し練習した形を試合で再現しやすくなります。これが、ビルドアップが目指す「再現性のある攻撃」の正体です。
ビルドアップのメリットと致命的なリスク【諸刃の剣を理解する】
ビルドアップは現代サッカーにおいて非常に強力な武器ですが、その一方で大きなリスクを伴う「諸刃の剣」でもあります。メリットを最大限に享受し、リスクを最小限に抑えるためには、その両面を正確に理解しておくことが不可欠です。ここでは、ビルドアップがもたらす具体的な利点と、一瞬で失点に繋がる致命的なリスクについて詳しく解説します。
メリット:チームが試合の主導権を握るための具体的な利点
ビルドアップを成功させることで、チームは以下のような数多くのメリットを得ることができます。
- 試合の主導権を握れる: ボールを保持することで、攻撃のテンポやリズムを自分たちでコントロールできます。相手にボールを渡さなければ失点することはない、というサッカーの原則を体現し、精神的にも優位に立てます。
- チーム全体で攻撃参加できる: 後方の選手から攻撃を組み立てるため、DFラインの選手も攻撃意識を持つようになります。チーム全体が同じ絵を描きながら押し上げることで、厚みのある攻撃を展開できます。
- 相手の体力を消耗させる: ボールを保持する側は比較的体力の消耗が少ないのに対し、ボールを追いかける守備側は心身ともに疲弊します。試合終盤、相手の足が止まってきたところで、生まれたスペースを突いて決定機を作り出すことができます。
- 攻撃の選択肢が増える: 相手を意図的に動かすことで、中央突破、サイド攻撃、裏へのスルーパスなど、多彩な攻撃パターンを状況に応じて使い分けることが可能になります。
リスク:失点に直結する4つの危険な罠と、その回避策
華やかなメリットの裏には、常に致命的なリスクが潜んでいます。特に以下の4つの罠は、どんなトップチームでさえ陥る可能性がある危険なものです。
- 自陣でのボールロスト: 最も危険なリスクです。自陣のゴールに近い位置でパスミスやトラップミスを犯すと、相手にとっては絶好のショートカウンターの機会となります。GKやCBのたった一つのミスが、即失点に繋がるケースはプロの世界でも頻繁に見られます。
- 相手のハイプレスに「ハマる」: ビルドアップを狙ってくるチームに対し、相手も前線から激しいプレッシャー(ハイプレス)をかけて対抗してきます。パスコースを限定され、複数人に囲まれてしまうと、逃げ場を失いボールを奪われてしまいます。これを「プレスにハマる」と表現します。
- ボール保持が目的化する: ビルドアップの本来の目的は「ゴールを奪うこと」ですが、繋ぐこと自体に固執しすぎると、いつの間にかボールを保持することが目的になってしまうことがあります。リスクを恐れて前へのパス(縦パス)を躊躇し、横パスやバックパスばかりになると、攻撃が停滞し、相手に脅威を与えることはできません。
- チームの連携不足による崩壊: ビルドアップは個人の技術だけでなく、チーム全体の組織的な連動が不可欠です。選手同士の意思疎通が取れていないと、パスの出し手と受け手のイメージがズレてしまい、簡単にインターセプトを許してしまいます。
これらのリスクを回避するためには、個々の選手の技術向上はもちろんのこと、「危険なエリアでは無理をしない」「相手のプレスが厳しい時はロングボールも選択肢に入れる」といった、チーム全体での状況判断能力と戦術的な柔軟性が強く求められます。
| メリット(得られる報酬) | リスク(伴う危険) |
| 試合の主導権掌握:自分たちのペースで試合を進め、相手を精神的に揺さぶることができる。 | 致命的なカウンター:自陣深くでボールを失うと、即座に失点に繋がるショートカウンターを浴びる。 |
| 効果的なスペース創出:相手守備陣を意図的に動かし、決定的なスペースを生み出すことができる。 | ハイプレスによる窒息:相手の組織的なプレスに捕まり、パスコースを失ってボールを奪われる。 |
| 攻撃の再現性向上:運に頼らず、トレーニングした形から安定してチャンスを作り出せる。 | 目的の形骸化:ボール保持自体が目的となり、ゴールを目指す意識が薄れ、攻撃が停滞する。 |
| チーム全体の攻撃参加:11人全員が攻撃に関与し、厚みのある多彩な攻撃を展開できる。 | 組織の崩壊:選手間の連携ミスや判断のズレが、簡単なボールロストと守備の破綻を招く。 |
ビルドアップを成功させるために不可欠な3つの要素
優れたビルドアップは、魔法のように生まれるわけではありません。それは、個々の選手の高度なスキル、瞬時の状況判断能力、そしてチームとしての緻密な連携という、3つの要素が完璧に組み合わさった時に初めて機能します。ここでは、ビルドアップを支えるこれらの不可欠な要素について、具体的な数値を交えながら解説していきます。
個のスキル:パス成功率94%超えの選手に学ぶ「止める・蹴る」の質
ビルドアップの土台となるのは、言うまでもなく選手個々の基本的な技術、特に**「ボールを正確に止める、蹴る」**というスキルです。自陣ゴール前というプレッシャーのかかるエリアでは、少しのズレが命取りになります。
- パスの精度: 味方が次のプレーにスムーズに移れるよう、スピード、回転、コースのすべてが完璧なパスを供給する能力が求められます。例えば、2023-24シーズンのマンチェスター・シティに所属するルベン・ディアス選手は、プレミアリーグで**94.1%**という驚異的なパス成功率を記録しました。このようなDFがいるからこそ、チームは安心して後方から攻撃を組み立てられるのです。
- トラップ(ファーストタッチ)の質: 相手のプレスが速い現代サッカーでは、ボールを受けた瞬間に次のプレーを選択できる位置にボールを置く技術が不可欠です。良いファーストタッチは、プレッシャーを回避し、プレーに時間的余裕をもたらします。
これらの基礎技術がなければ、どんなに優れた戦術も絵に描いた餅に終わってしまいます。
状況判断能力:ピッチを俯瞰し、最適解を導き出す「認知」の力
優れた技術を持っていても、それをいつ、どこで、どのように使うかを判断できなければ意味がありません。ビルドアップにおいて次に重要になるのが、ピッチ全体の状況を正確に「認知」し、瞬時に最適解を導き出す状況判断能力です。
選手はボールを保持しながら、あるいはボールを受ける前に、以下のような情報を常に収集・分析しています。
- 味方選手の位置はどこか?
- 相手選手はどこにいて、どのようにプレッシャーをかけてきているか?
- ピッチ上のどこにスペースが生まれているか?
- リスクを冒して縦パスを入れるべきか、安全にサイドへ展開すべきか?
特に、チームの心臓部であるボランチの選手には、360度からのプレッシャーの中で常に首を振り、ピッチを俯瞰で見るような広い視野が求められます。この認知と判断のスピードと正確性が、ビルドアップの質を大きく左右するのです。
組織的な連携:「三人目の動き」に見るオフ・ザ・ボールの神髄
個人のスキルと判断力が揃った上で、最後に必要となるのがチームとしての組織的な連携です。ビルドアップは、ボールを持っている選手(オン・ザ・ボール)だけで行うものではありません。むしろ、ボールを持っていない選手(オフ・ザ・ボール)の動きこそが、その成否を分けます。
その代表例が**「三人目の動き(Third Man Run)」**と呼ばれるプレーです。これは、以下のような連動した動きを指します。
- 選手Aが選手Bにパスを出す(一人目の動き)。
- 選手Bは、相手のマークを引きつけながら、選手Aにボールを落とす(レイオフパス)か、近くの選手にシンプルにパスを出す(二人目の動き)。
- その間に、全く別の選手Cが、相手のマークが外れたスペースへ走り込み、選手A(またはB)からのパスを受ける(三人目の動き)。
この動きによって、相手のプレスをいなし、前を向いたフリーの選手を作り出すことができます。これは、選手同士が「次にどこにスペースが生まれるか」を予測し、共有できていなければ成立しません。このように、複数の選手が同じ絵を描き、連動することで、ビルドアップは初めて機能的なものとなるのです。
【図解】ビルドアップの基本パターンと各ポジションの役割
ビルドアップは、各ポジションの選手がそれぞれの役割を正確に理解し、遂行することで成り立ちます。ここでは、ゴールキーパーからフォワードまで、それぞれのポジションがビルドアップにおいてどのようなタスクを担っているのかを、具体的な戦術パターンを交えながら解説します。
GK(ゴールキーパー):攻撃の第一歩を踏み出すフィールドプレーヤー
現代サッカーにおいて、GKは単なる「シュートを止める選手」ではありません。ビルドアップにおいては**「11人目のフィールドプレーヤー」**として、攻撃の第一歩を踏み出す極めて重要な役割を担います 1。最後方からピッチ全体を見渡せるGKは、相手のプレスの状況を最も冷静に判断できるポジションです。
- 主な役割:
- 数的優位の創出(相手FWに対して+1の状況を作る)。
- 相手のプレスの第一波を回避するための、安全なパスの供給源。
- 状況に応じたショートパスと、相手の裏を突くロングフィードの使い分け。
マンチェスター・シティのエデルソン選手のように、足元の技術とキック精度に優れたGKの存在は、チームのビルドアップの質を飛躍的に向上させます。
CB(センターバック):パスの供給源とプレス回避の要
CBは、GKからボールを引き出し、中盤へパスを供給するビルドアップの中心的な役割を担います 1。相手FWのプレッシャーを直接受けるため、冷静な判断力と高い技術が求められます。
- 主な役割:
- ペナルティエリアの幅まで大きく開くことで、パスコースを作り出し、相手FWのプレスを困難にする。
- ボランチやサイドバックへ、相手の足を止め、次のプレーに繋がりやすい「良いパス」を供給する。
- 時にはドリブルでボールを運び、相手の中盤選手を引きつけて数的優位を作り出す。
SB(サイドバック):幅の確保と攻撃の出口を担うキーマン
SBは、ピッチの横幅を最大限に使い、チームに攻撃の幅をもたらす重要な役割を担います。タッチライン際にポジションを取ることで、相手の守備組織を横に広げさせ、中央にスペースを生み出す効果があります。
- 主な役割:
- 高い位置を取ることで、相手陣内に押し込む起点となる。
- CBやGKからのパスの「出口」となり、プレッシャーを回避する。
- 後述する「偽サイドバック」のように、中央に入ってきて中盤のパス回しを助けることもある。
ボランチ(守備的MF):サリーダ・ラボルピアーナに見るチームの心臓部の動き
ボランチは、守備と攻撃を繋ぐチームの心臓部です。DFラインからパスを引き出し、前線の選手へと展開する、ビルドアップにおける最重要中継地点と言えます。
- 主な役割:
- 常にパスコースを作り、ボール保持者をサポートする。
- 相手のプレスをいなし、攻撃の方向性を決定づける。
- 広い視野で戦況を把握し、ゲームをコントロールする。
ビルドアップの有名な形の一つに**「サリーダ・ラボルピアーナ(La Salida Lavolpiana)」**があります。これは、ボランチの選手が2人のCBの間に下りてきて、一時的に3バックのような形を作る動きです。これにより、両SBが高い位置を取りやすくなり、後方でのボール回しも安定するという利点があります。この動きは、ビルドアップにおけるボランチの重要性を示す象徴的なプレーと言えるでしょう。
| ポジション | 主な役割 | 求められるスキル | 選手例 |
| GK | 攻撃の起点、数的優位の創出 | 正確なショートパス、ロングフィード、冷静な判断力 | エデルソン(マンチェスター・シティ) |
| CB | パスの供給源、プレス回避 | パス精度、対人守備、ボールを運ぶドリブル | ルベン・ディアス(マンチェスター・シティ) |
| SB | ピッチの幅の確保、攻撃の出口 | 上下動を繰り返す持久力、正確なクロス、戦術理解度 | カイル・ウォーカー(マンチェスター・シティ) |
| ボランチ | チームの心臓、攻守の繋ぎ役 | 広い視野、パス展開力、危機察知能力、ボール奪取力 | ロドリ(マンチェスター・シティ) |
【戦術の最前線】トップチームが実践する先進的なビルドアップ戦術
ビルドアップの基本を理解した上で、最後に現代サッカーの最前線で繰り広げられている、より高度で革新的なビルドアップ戦術の世界を覗いてみましょう。ロベルト・デ・ゼルビ監督やシャビ・アロンソ監督といった名将たちは、ビルドアップを芸術の域にまで高め、サッカーの新たな可能性を切り拓いています。
デ・ゼルビ監督の哲学:「相手を誘い込み、背後を突く」ブライトン式ビルドアップ
元ブライトン監督のロベルト・デ・ゼルビは、ビルドアップにおいて最も革新的な指導者の一人として知られています。彼の哲学の核心は、**「意図的に相手のプレスを誘い込み(誘引)、その背後に生まれたスペースを一気に突く」**というものです。
デ・ゼルビのチームは、GKやCBが自陣のゴール前で、あえてボールを足裏で止めたり、ゆっくりとパスを回したりします。これは、相手に「奪えるぞ!」と思わせて、前がかりにプレスをかけさせるための**「罠」**です。相手がその罠にかかり、食いついてきた瞬間、プレスに出てきた選手の背後にできた広大なスペースへ、素早く縦パスを打ち込みます。
この戦術は、自陣でのボールロストという最大のリスクと隣り合わせですが、成功すれば相手のプレスを無力化し、一気に決定的なチャンスを迎えることができます。まさにハイリスク・ハイリターンを体現した、スリリングなビルドアップ戦術と言えるでしょう。
シャビ・アロンソ監督の原則:「相手の守備列を越える」ための組織的ポジショニング
2023-24シーズンにバイエル・レバークーゼンを無敗優勝に導いたシャビ・アロンソ監督のビルドアップは、**「相手の守備ブロックの『列』を一つずつ越えていく」**という原則に基づいています。
彼のチームは、ボール保持者に対して常に複数の選手がサポートに入り、常に3つ以上のパスコースを確保することを徹底します。選手たちは決して止まることなく動き直し、相手の守備網の中に絶えずパスコースを作り続けます。
そして、ただ闇雲に前に進むのではなく、相手のFWのラインを越えるパス、次にMFのラインを越えるパス、というように、安全かつ確実に相手の守備の「列」を突破していきます。もし前進が難しいと判断すれば、無理をせずにバックパスを選択し、もう一度体勢を立て直します。この粘り強いポジショニングとパスワークによって、相手に付け入る隙を与えず、試合を完全に支配するのです。
現代戦術の鍵:「偽サイドバック」がもたらす中盤の革命
近年、ビルドアップの戦術を語る上で欠かせないのが**「偽サイドバック(Inverted Fullback)」**という概念です。これは、本来サイドに張るべきSBが、ビルドアップ時に内側(中央)のポジションを取り、ボランチのように振る舞う役割を指します。
この動きには、主に3つの戦術的メリットがあります。
- 中盤での数的優位: SBが中央に加わることで、相手の中盤に対して数的優位を作り、パス回しを安定させます。
- ウイングへのパスコース創出: 相手のサイドハーフが、中に絞ってきたSBをマークするために中央へ移動すると、外側のウイングへのパスコースが大きく開きます。これにより、ウイングの選手は有利な状況でボールを受けられます。
- カウンター対策: SBが中央にいるため、ボールを失った際に相手のカウンターの最短ルートである中央をすぐに塞ぐことができ、守備の安定性が増します。
この戦術は、マンチェスター・シティを率いるペップ・グアルディオラ監督が完成させ、現在ではアーセナルの冨安健洋選手など、多くのチームや選手が採用する現代サッカーのスタンダードとなりつつあります。
まとめ:ビルドアップは目的ではなく、勝利というゴールへ至るための「手段」である
ここまで、サッカーにおけるビルドアップの定義から目的、リスク、そして最先端の戦術に至るまで、多角的に解説してきました。
ビルドアップとは、単に後方でボールを回す作業ではなく、「ゴールを奪い、試合に勝利する」という最終目的を達成するために、数的優位やスペースを意図的に作り出しながら、チーム全体で攻撃を組み立てる緻密なプロセスです。
しかし、最も重要なことは、ビルドアップという戦術そのものを絶対視しないことです 2。それはあくまで勝利を手にするための数ある**「手段」**の一つに過ぎません。チームの選手の技術レベルや特徴、対戦相手の戦術、試合の状況によっては、ビルドアップに固執することがかえってリスクを高める場合もあります。時には、相手のハイプレスを回避するために一本のロングボールを選択する柔軟性も、優れたチームには必要不可欠です。
指導者や選手が「なぜビルドアップを行うのか?」という本質的な目的を常に共有し、そのメリットとリスクを天秤にかけながら、状況に応じた最善の選択を下していく。その先にこそ、ビルドアップという戦術の真の価値が生まれるのです。
この記事を通じて、皆さんのサッカー観戦が、ピッチ上で繰り広げられる選手たちの意図や監督の戦術的狙いを読み解く、より深く、知的な楽しみへと変わる一助となれば幸いです。
↓こちらも合わせて確認してみてください↓
-新潟市豊栄地域のサッカークラブ-
↓Twitterで更新情報公開中♪↓
↓TikTokも更新中♪↓
↓お得なサッカー用品はこちら↓
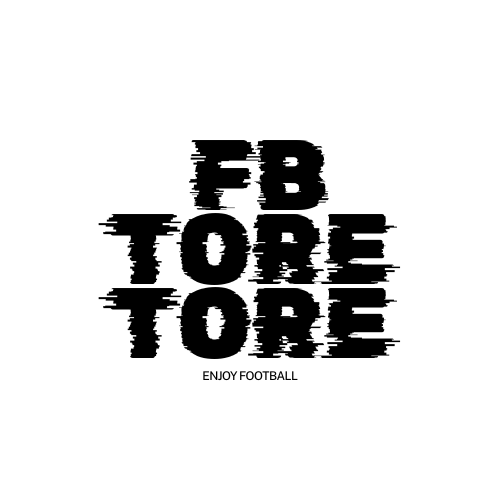



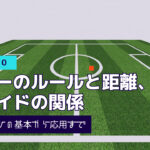
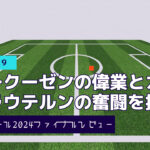


コメント